



 |
 |
 |
 |
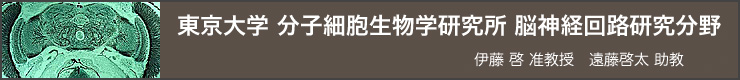
|
バックグラウンド ー なぜ神経の解剖学なのか。なぜショウジョウバエなのか。現代生物学は、遺伝子のクローニングや、突然変異やノックアウト生物を用いた研究が花盛りである。その中で我々は、細胞を同定したり、その細胞が線維を伸ばす過程を観察して詳しく記載するという、ちょっと学問の主流から離れた、地味な作業を行なっている。なぜこんなことをしているのだろうか。 精緻な記載的作業の大切さマウスが4本足であることは、誰でも知っている。だからもし6本足のマウスを見つけたら、異常があるとすぐに分かる。いっぽうマウスの肋骨の本数は、誰でもすぐに答えられるものではないが、教科書をちょっと見れば書いてある。だからノックアウトマウスの肋骨が増えたり減ったりしていたら、研究者なら誰でもすぐに異常に気がつく。ちょっと注意深い研究者なら、何本目の肋骨に異常が起きたかも、ちゃんと分かるだろう。 ところが、脳の細胞はどうだろう?どこに、どのような細胞が、いくつ位あるのか。どの細胞は、どこからどこへ線維を伸ばしているのか。「異常」を研究するには、「正常」な状態がきちんと分かっていることが大前提だが、脳の研究では、この基本的条件が、まだ満たされていない。だから、突然変異などで異常が生じた脳を見ても、どこにどのような異常が生じているのかを、細胞レベルできちんと特定することができないし、脳の中のある特定の細胞が、変異によってちょっと増えたり減ったりしていても、研究者はそれに気付くことができない。 昆虫からヒトまでたいていの実験動物には、脳のアトラスというものが出版されている。これらはしかし、銀染色などの古典的な技法を使って、脳のどの部分をどういう名前で呼ぶかを示した、大まかな地図にすぎない。ひとつの脳領域には、同じような細胞が漫然と並んでいるわけではなく、様々な形をした非常にバラエティーに富む細胞群が、複雑な回路構造を形成しているのであるが、これらの細胞の詳しい形態、数、投射パターンがきちんと調べられている例は、非常に少ない。 確かに従来の学問にとっては、この程度のアトラスでも、必要十分であった。しかしいまや分子生物学の進歩によって、ある遺伝子が発現している細胞を、抗体や in situ ハイブリダイゼーションを使って、染め分けられるようになった。ある神経細胞が染まって、そのすぐ隣の神経細胞が染まっていないことはよくある。染まった細胞は何をしている細胞なのか、染まった細胞と染まっていない細胞は何がどう違うのか、従来のアトラス程度の記載では、とうてい十分な情報が得られない。 脳神経系の分子生物学的解析をさらに発展させてゆくためには、より細かいレベルでの精緻な記載的知識を、誰かが提供する必要があるだろう。 重箱を、隅から隅までつつく精緻であることと並んで、もう一つ大事なことがある。体系的に、網羅的に記載することである。当面必要なところ、興味を引くところだけでなく、とりあえず必要なさそうなところまでも、密度の差はあれ、全て調べてある必要がある。なぜならば、そうしないと全体像が把握できないからだ。 国土地理院が提供する地形図には、普通の人が絶対行かないような所までも、丹念に測量され、収載されている。このような一見無駄な記載があって初めて、日本という国の地形の全体像が把握できる。ある地形が日本にはありふれたものなのか、1ケ所しかない特殊なものなのか、珍しいが数ヶ所程度はあるものなのかを、言うことができる。 細かいところを切り捨てて、本質だけを抜き出して調べるというのは、科学の重要なアプローチのひとつだ。だが、何が本質で何が些末かを知るためには、全体像が分かっていなくてはならない。脳を調べるときも、目に付きやすい太い線維や、整然とした回路構造だけでなく、線維が複雑に絡み合った一見不規則に見える領域や、細かな線維の接続なども調べておかないと、本質を見誤る危険がある。 「オーミクス」は、解剖学では300年前から当たり前近年生物学研究の中でひそかな(?)ブームになっているのが、「オーミクス」と呼ばれる分野である。個々の遺伝子(gene)でなく全ての遺伝子で構成される全体像として、語尾をomeに変えたゲノム(genome)という言葉が創られ、それを解析する学問分野として、語尾をomicsに変えたゲノミクス(genomics)という言葉が産まれた。ゲノム解析が順調に発展するにつれ、同じアプローチの応用としてタンパクの全体像としてのプロテオーム、表現型の全体像としてのフェノーム、代謝物の全体像としてのメタボロームなどの単語が創られ、「新しい」研究分野として注目されるようになった。 一方、解剖学では「アナトーム」とか「アナトミクス」などという言い方はしない。昔から「アナトミー」である。なぜだろうか? 遺伝子やタンパクや表現型解析や代謝解析の分野では、技術的な制約もあったため、何かのきっかけでたまたま研究者がその存在を知ることができた一部の遺伝子・タンパク・表現型・代謝物などについて詳しく解析するが、他にどういうものがあるかについては、分からないからひとまず置いておこうというのが従来の研究手法だった。これは、たとえて言えば右側の3本目の肋骨についてだけ詳しく調べているのだが、肋骨というものが全部で何本あるのかはよく分からない、という状況に似ている。これでは良くない、ということで、進歩した技術を駆使してもっと全体像を研究しようというのがオーミクスである。 一方、解剖学のセンスでは、人間にある200個の骨のうち、何本かの骨には名前もついてないなどということはそもそもあり得ない。存在するものはすべて同定し、すべてに名前を付け、それぞれがどのような特徴があるかをすべて調べて記録するのが、解剖学の基本的なアプローチである。今から300年近く前の1722年に発行されたターヘルアナトミア(解体新書の元版)ですら、存在する全ての解剖学的事象について体系的にまとめようという、今で言えばオーミクス的な視点で書かれている。最初からこうした全体像を解明するのが目的だった学問を、今さらアナトミクスなどと名前を置きかえる必要はなかった。 実のところ、仲間うちのコアな解剖学の研究者たちと「アナトミーでなくアナトミクスという名前でも提唱すれば、モダンな学問という感じがしてもっと人気が出るかもね」という話をしたことがある。結論は「でも、そもそも全体像を解析する学問なのに、新しい名前をつけたって何も変わらないではないか」ということになった。この話をしたのは1996年のイギリスの学会でのことである。それから10年以上も遅れて他の分野の人たちが急にオーミクスと騒いでいるのを見るのは、とても不思議な気がする。 解剖学の中でも、技術的な問題から従来は「ごく一部だけを解析する」ことしかできなかった分野では、近年になってわざわざオーミクス的な発想を取り入れたと宣伝しているケースもある。たとえば電子顕微鏡でシナプスを観察するという学問は、撮影倍率があまりにも高いため、神経組織のごく一部しか解析できないのが当たり前だった。最近になってやっと、多数の画像をまとめてかなり広い範囲のシナプスの全体像を解析する技術的な目途が立ち始めたため、神経接続の全体像という意味で「コネクトーム」という言葉が創られている。やっと追いついてきたか、という感がある、 複雑なものの一部より、単純なものの全体脳と言えばヒト、ヒトといえば哺乳類、哺乳類といえば脊椎動物である。マウスなどの脊椎動物は、人を研究するモデルによく使われている。こんなときに、あえてヒトとはかけ離れた昆虫などを調べようとするのはなぜなのか。同じように精緻で体系的な記載作業をするのならば、ハエなどでなく、マウスの脳を細かく記載した方がいいのではないだろうか。 脳について現在科学者が持っている知識は、ちょうど小学生が電子回路について持っている知識と同じようなものである。スーパーコンピューターの回路ボードをいきなり小学生に与えて、回路図を描きおこせと言ってみても、彼らには難しすぎる。まずはラジオや簡単なゲーム機を作ったり壊したりして、電子回路の動作の基本原理が理解できるようになって初めて、複雑な電子機器の回路も解析できるようになる。 まず単純な系から理解しようという場合、二つのアプローチがあり得る。一つは、複雑な系の一部分をなすサブシステムに着目する方法だ。たとえば海馬の神経回路を「ぜんぶ」調べる。前頭前野の神経回路を「ぜんぶ」調べる、というような研究である。このような研究はもちろん非常に大切だ。しかしこの場合、着目した脳領域に、他のどのような脳領域から、どのように前処理された情報が入力されているのか、また出力は他のどのような脳領域に伝えられ、どのように後処理されて最終的な行動制御に結びついているのか、これらについては知ることができない。接続されている相手先の脳領域について、まだ十分な知識がないからである。入力信号と出力信号の性質が分からなくては、回路の動作原理をきちんと解析することは難しい。また、着目した脳領域の回路や動作が、脳全体の機能を代表するような部分であるのか、例外的な動作をしている一部分であるのか、保証はない。 もう一つのアプローチは、シンプルな脳を持つ生物に着目し、その脳の全貌を解析する方法だ。昆虫の脳は、脊椎動物の脳よりも細胞数がずっと少なく、大きさも小さい。顕微鏡の視野に全体が入る程度のサイズながら、かなり難しい情報処理もこなしている。このような回路は、細胞数も複雑さも、今の科学者の知識レベルに対して、ちょうど手頃なモデルになるだろう。 神経細胞が300個と非常にシンプルな線虫では、神経系全体の回路図がすでに明らかにされている。しかし線虫は行動パターンも限られ、脳と呼ぶにふさわしい密集した中枢神経構造もない。いっぽう数億からの細胞からなるマウスやラットで、脳全体の回路図を作成し、コンピューターでシミュレーションするようなことは、現代の我々の知識・技術レベルでは、ちょっと非現実的だ。数万の細胞数の昆虫の脳ならば、回路図を作ってシミュレーションすることも、それほど非現実的ではない。 ヒトやサルに対しては、言葉や絵文字を使ってコミュニケーションしたり、複雑な課題をやらせたりすることができる。しかし同じ脊椎動物といってもラットやマウス、ニワトリ、サカナでは、複雑な芸を仕込むことも、コミュニケーションを取ることもできない。従って、これらの動物を使って学習などの脳機能解析のために行なわれている行動実験は、ごく単純なものに限られてしまっている。ラットの脳は昆虫の脳よりもはるかに複雑な情報処理をしているのであろうが、実際のところ、ラットで行なわれている行動実験のほとんどは、昆虫を使っても実施されている程度のものなのだ。同じ程度の機能解析実験しかできないのならば、シンプルな脳の方が、より早くメカニズムを解明できることだろう。 見かけの違いにまどわされないだが昆虫の脳には、海馬もないし小脳もない。全体の回路構造があまりにも違うから、そんなものを調べてもヒトの脳の仕組みを知るには、あまり意味がないのではないか、という考え方もあるかもしれない。 しかし現代生物学の歴史は、見かけの違いに惑わされず、シンプルな系に着目することの重要性を示している。初期の分子生物学者は、それまで遺伝学者がなじんでいたショウジョウバエや植物ではなく、アカパンカビやファージという、およそ我々とはかけ離れた姿をした生物を、研究対象に選んだ。これらの生物を使わずに、もしショウジョウバエや植物でいきなり分子生物学をやろうとしていたならば、ヒトのガンを引き起こす遺伝子について現在の我々が持っている知識は、いまだに極めて限られていたであろう。 同じように、昆虫の脳とヒトの脳は、全体の構成はだいぶ異なるが、情報処理装置としての基本的な動作原理は、共通な部分が多いはずだ。じっさい昆虫と哺乳類の、視覚や嗅覚の感覚情報処理部の構造を見ると、形態は全く違うものの、回路のつながり方のレベルでは、共通点が非常に多い。私たちはこれまでショウジョウバエの各種の感覚神経系の構造を集中的に調べてきたが、五感のうち視覚・嗅覚・味覚・聴覚/重力感覚の4つについては、感覚器の構造はヒトとハエでずいぶん異なるにもかかわらず、そこからの情報を処理する低次感覚中枢は驚くほど類似した神経回路を持っていることが分かってきた。(触覚/体感覚の研究はこれからである。) 従って、シンプルな昆虫脳を用いてヒトにも共通するような基本的な回路の構造と動作メカニズムをきちんと理解してから、ヒトにしかないような複雑な脳機能の解析に挑むというのは、それほど遠回りなアプローチではない。 違うものを調べることで、自分自身のことを知る私たちはなぜ、英語を学んだり、他の国の歴史について学んだりするのだろうか?単に海外旅行に行ったときに会話がしやすいようにとか、名所旧跡について蘊蓄を垂れることができるようにということが目的ではない。フランスのある科学者が、「世界の言語の中でフランス語だけが唯一合理的な言語である。頭で考えた順番通りに単語が並んでいるのは、フランス語だけだからだ。」と言ったそうである。これがうさんくさい理論であることはすぐに分かる。世界の言語で、名詞や形容詞や副詞の順番がこれほど様々であるということは、そういうことは「言語」というものの特性の中で二義的なものであって、思考の概念形成の過程とは独立であるということだ。同じ概念を伝えているのに語句の構成がずいぶん異なる「私は野球が上手です。」と「I am a good baseball player.」という中学一年レベルの文章を比較するだけで、「私は」や「野球が」という言葉がどういう機能を担っているかを、深く考えることができる。日本語だけを研究しているのでは見逃してしまういろいろなことが、他の言語を学ぶことで改めて分かってくるわけである。歴史や経済でも同じである。ある特定の国のことだけを調べていたのでは、その国に見られる様々な特徴が、その国独自の特殊な事情で産まれた独特なものなのか、それとも「人類が構成する社会というもの」に普遍的に存在するものなのか、区別ができない。深く影響しあった似たような国同士(たとえば西洋だけとか)を比べても、こういうことは分からない。遠く離れて全く異なる発展を遂げた国同士を比較することで、より普遍的な概念を構築することができる。 この点からは、ヒトの脳を理解するのにマウスや鳥類、魚類の脳を使うのは、あまり効果的ではない。これらは進化の上でヒトの脳の直系の類縁であって、本質的に似ていて当たり前だからである。ラテン語とイタリア語、鹿児島弁と東京弁を比べるようなものだ。 ヒトの先祖とハエの先祖は約6億年前に分かれたとされている。そのころすでに、光・化学物質・物理的な力などを感じるための分子機構や、細胞内電位変化とシナプスを使って情報を処理する神経細胞というものは存在していた。そのような共通の先祖から産まれたのだから、ヒトとハエの神経系が分子レベルで多くの相同性を持っているのは、驚くには当たらない。一方、当時の生物はまだ前後方向の体軸というものが確立しておらず、中枢神経系というものも存在しなかった。同じような生理学的特性を持った「感覚細胞」「神経細胞」というものを使って、外界の情報を処理して最適な行動を制御するようなシステムを作るには、様々な方法があったであろう。6億年の時を経て、ことなる試行錯誤の過程を経て作られたシステムを比べることで、私たちの脳が持っているさまざまな構造的特徴のそれぞれが「脊椎動物の末裔としての哺乳類のひとつの種」に特有な特殊な事情で産まれた独特なものなのか、「神経細胞という素子を使って構築する情報処理システムというもの」に普遍的なものなのかを、初めて区別して理解することができる。 モデル動物であることの重要性昆虫脳を調べるといっても、なぜキイロショウジョウバエを使う必要があるのだろうか。昆虫の神経解剖学・神経生理学の歴史では、ショウジョウバエは常に少数派であった。ガ、チョウ、ゴキブリ、コオロギ、ハチなどが主役であり、ハエは大型のイエバエやクロバエが使われるときの方が多い。ショウジョウバエは非常に小さいので、電気生理の実験で電極を刺すのは至難の業だし、ハチやガのようなテレビの教養番組でも受けるような興味深い行動パターンを示すこともなく、どちらかといえば退屈な昆虫だといえる。 にもかかわらず、キイロショウジョウバエの脳を精緻に記載することに特別な意義があるのは、この生物がモデル動物であるからである。モデル動物という言葉には2つの意味あいがあって、単に、ある特定の研究テーマに好適な性質を持つ動物、という意味で使われることも多い。しかし厳密な意味でのモデル動物とは、その動物について世界中の多くの研究者が、発生学・解剖学・生化学・遺伝学・突然変異コレクション・ゲノム解析など多くの側面について、組織的に研究している動物を指す。これに該当するのは、線虫、キイロショウジョウバエ、ゼブラフィッシュ、マウスなど、ごく限られた数種類の生物だけである。 同じ努力をして、精緻に体系的な解剖学の解析をするのならば、その成果が多くの分野の、多くの研究者の役に立った方がよい。脳構造に異常がありそうな突然変異の解析や、脳のどこかで発現していそうな遺伝子のクローニングが盛んに行なわれている実験動物を使ってこそ、精緻な記載が実際に役に立つ。従って、ハチやガの脳の記載的解析をするのと、キイロショウジョウバエの脳の記載的解析をするのでは、持つ意味あいが本質的に異なる。アナナスショウジョウバエなどの近縁種でも駄目で、「キイロ」ショウジョウバエでなくてはいけないのだ。 比較解剖学的な視野の広さの大切さとはいえ、キイロショウジョウバエの脳だけを見ていればよいというものでもない。脳とは、神さまが動物種ごとに設計図をひいて作ったものではなく、長い進化の歴史を経て、原始的な構造に徐々に改変が加えられて作られてきたものである。従ってそれぞれの脳回路構造は、その動物種がたどってきた長い進化の過程を反映している。 ショウジョウバエの脳にも、またハチの脳にも、その昆虫だけに特殊な構造もあれば、昆虫界全体に共通する構造もある。一つの種で見つかった構造や現象を、昆虫全体に通用するものと乱暴に仮定することは、よくない。また昆虫種の違いによる行動パターンの違いと、脳構造の違いを比較することは、その部分の回路の機能を推定する上で、重要な情報になる。一つの種の脳だけを見ていたのでは、このような差は分からない。あくまでキイロショウジョウバエの脳を中心に解析するにしても、他の昆虫(や他の節足動物)の脳解剖学も、視野の端に入れておくことが欠かせない。 コンピューターの類推から脳を理解しようとすることの難しさ21世紀初頭という時代に生きる私たちが手にしたもっとも高度で複雑な技術的成果は、コンピューターというものであろう。1946年に実用化して以来、一部の領域ではヒトの脳を追い越すレベルの情報処理までも可能にしたコンピューターは、「人工知能」という言葉を産み、コンピューターと比較することでヒトの脳も理解できるのではないかという期待もふくらんでいる。 だが過去を振り返ると、昔の科学者たちは脳をパイプオルガンや蒸気機関と比較してきたという歴史がある。何のことはない、その時代時代でもっとも複雑でややこしく見えるキカイと、脳を比べてきたのである。21世紀に生きる私たちは、脳をパイプオルガンと比較した17世紀の科学者を稚拙と笑ってしまう。だが25世紀の人たちが、脳をコンピューターと比較した20世紀21世紀の科学者を稚拙だと笑わない保証はどこにもない。 コンピューターはしょせん人間が作った機械であって、人間が指示したとおりにしか動かない。自分で問題解決をするように作られたコンピューターであっても、そういう動作をするように人間が予めプログラムしただけのことである。コンピューターのチェスプログラムは人間のチェスプレーヤーを凌駕するようになった。これを「現代のコンピューターはついに人間を越えた」と考える人もいるが、それは違う。チェスのグランドマスターを越えたのはコンピューターではなく、ついに人間のチェスプレーヤーを凌駕するようなプログラムを書けるようになった人間のプログラマーと、そのプログラムを実用的な速さで実行できる高速コンピューターを実現した人間の設計者である。コンピューターが自分でプログラムを書けるようになったわけでも、自分で新型のコンピューターを作れるようになったわけでもない。 コンピューターに限らず、20世紀の人間は自分の身体能力の一部を補う優れた機械をいろいろ実用化してきた。自動車は馬よりも速く、馬よりも重いものを運ぶことを可能にし、飛行機は鳥よりも速く、鳥よりも重いものを運ぶことを可能にした。だが、馬と違って自動車はわずかな障害物もジャンプして飛び越すことはできないし、飛行機は木の枝に止まることができない。馬が動く仕組みを自動車をモデルにして理解したいと言ったら、笑われてしまうだろう。馬はエンジンもトランスミッションもタイヤも使っていないし、馬が持つ運動能力の中で自動車というものが代行可能にしたのは、ごく一部の機能に過ぎないからである。同じように、CPUとメモリーと長期記憶装置という人間とは全く違う部品で構成され、数字の処理という特殊な機能に特化し、予め設計されたフォンノイマン型のプログラムに書かれていないことは実行できないコンピューターという機械は、馬と自動車が違うのと同じ程度に、脳とは似ても似つかないものである。所詮は人間が作ったキカイであって、それをもとに脳が理解できるというようなものではない。今のコンピューターではとても脳のかわりにならないからこそ、私たちは脳を研究しているのである。 私はもともと、大学の学部4年までは物理学を専攻していた。量子力学の大統一理論に落ちこぼれたのと脳や神経に興味を持つようになったことで生物学の分野に移ってきたが、当時は人工知能を開発する「第五世代コンピュータープロジェクト」というのが話題になっていた。これはLISPやPROLOGといった人工知能言語を使って人間の論理思考を実現するコンピューターを作ろうというものだったが、多くの人材を育成するという点では成功したものの(今のバイオインフォマティクスの研究者にはこのプロジェクトの出身者も少なくない)、研究そのものとしては決して成功したとは言えない。当時の私も、こんな手法で人間の思考を理解できるとは思えなかった。 物理学を学んで思ったのは、「自分が知らないことについて考えるには、まず事象をきちんと計測し、体系的に全体像を把握することが本質的に大切である」ということである。孔子は「学んで思わざるは即ち罔し、思うて学ばざれば則ち殆し」と言った。観測データを記録する(学ぶ)だけでそれが何を意味するのか一般化した理論を考察しない(思わない)のは「くらい」が、あれこれ理論を考える(思う)だけで現実の事象を十分に観察しようとしない(学ばない)のは、机上の空論になって「あやうい」。ティコ・ブラーエが惑星の運行をかつてない精度で測定したからこそ、そのデータを使ったケプラーは天動説でなく地動説に基づいた惑星運行の概念を得ることができた。空気抵抗や摩擦の影響を排除した定量的な測定を行ったからこそ、ガリレオはアリストテレスの定性的で文学的な理論の誤りを正すことができた。自分がよく分かっていない事象に対して、自分の思いつきを正当化できるような一部分だけの知識から都合の良い解釈をするのは、あまり「物理学的」ではない。脳というものがまだ皆目よく分からない情況の中で、きちんと測定できるものを体系的に測定して基本的なデータを収集するという点で私がもっとも物理学的だと思ったのが、情報処理の基本素子である神経の回路構造をきちんと理解しようということであった。コンピューターはそのために不可欠なツールではあるが、それはピンセットや顕微鏡と本質的に同じ「道具」に過ぎない。 とはいえ、コンピューターは単に観測データを得るのに便利なだけではない。観察して分かった神経回路が実際どのように動作するのかを考えるには、その回路特性を再現したモデルをコンピューターの中に作り上げ、動作シミュレーションの結果を実際のサンプルの観察結果と比較するのが有効だろう。このようなコンピューターシミュレーションは、核物質の反応や大気の循環など様々な分野で効果を発揮してきた。このようなツールとして、神経科学の分野でもコンピューターの利用価値は大きい。 突然変異を解析しないということ生物の話に戻る。解剖学を初めとする記載生物学というのは、19世紀末以来死に絶えた学問分野と思われている。有力な学術雑誌には、記載的な論文は掲載しないという方針を打ち出しているものも少なくない。確かに、観察して、記録するだけのこの学問は、小学生の夏休みの自由研究と、変わるところがないかもしれない。 漫然と手持ちの実験材料と実験技術を使って、観察できるものを観察しているだけであれば、小学生と差はない。しかし何を、どのように観察し、記載するかを吟味するセンスを持ち、現代生物学がさらに発展するために不可欠な基本的知識を、タイムリーに提供できるならば、記載生物学は決して過ぎ去った学問ではない。遺伝子をクローニングして、その遺伝子が○○モチーフを持っていて他の生物の△△遺伝子とxxパーセントの相同性があると報告するなどというのは、実は新しく見つけた遺伝子を「記載」しているに過ぎない。新しく見つけた生物種を記載する分類学や、新しく見つけた神経を記載する脳解剖学と、全く同じである。記載とはいつの世でも、何かを知るためには本質的に大切なものなのである。科学の歴史とは、つまりは人類が知らなかったことを「記載」する営為の歴史である。 体系的で精緻な記載を、網羅的に行なっていく作業には、大変な手間と時間がかかる。一つの研究グループがこのような作業を行なうためには、何かを犠牲にしなくてはならない。ショウジョウバエを使った研究では、突然変異系統の作成と解析や、遺伝子のクローニングが主流である。脳の研究では、すでに誰かが同定した特定の神経細胞について、その発生メカニズムや生理学的な機能を調べる研究が脚光を浴びている。だが、遺伝子さえ調べれば脳が分かるというものでもない。また、誰かが見つけた神経をみんながよってたかって研究しているだけでは、研究できることは早晩研究し尽くされてしまい、近いうちに煮詰まってしまうのは明白である。しかもこれらの分野は、競争が熾烈だ。これは裏を返せば、その仕事を別に自分がやらなくても、他の誰かが必ずやってくれるということである。「かわりはいくらでもいるもの」という綾波レイのような研究である。このような、別に自分じゃなくてもできるような研究ではなく、誰もが必要だと思いながらなかなかやらないような地道な仕事をやり、狭い袋小路でなく全体像を眺め、よってたかってひとつの神経を研究している人たちが煮詰まったときに、次に研究したくなるような興味深い神経システムを予め見つけておいてやって次の研究のネタを提供してあげることは、それ自体けっこう面白いものであるうえに、自然科学への大切な貢献だと思う。 (伊藤 啓)
|
